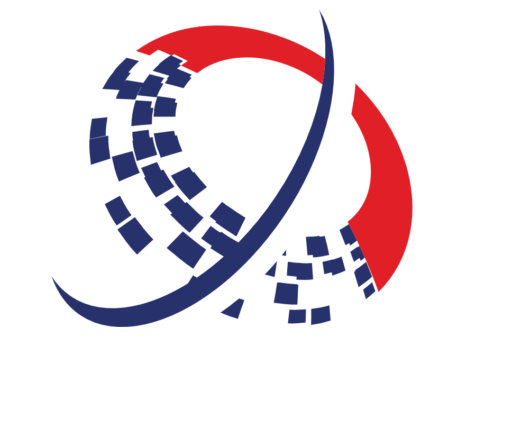地球から1億5000万キロも離れながら、肉眼で直接見るのは危険なほど輝き続ける太陽。莫大な熱と光のエネルギーを地球に届け続け、われわれの日常生活を支えている。もし太陽が突然消えてしまったり、地球との距離がわずかでもずれてしまったりすれば、その途端に人類はおろか地球上のあらゆる生命が生存できなくなることだろう。そんな太陽と同様の核融合反応を利用して膨大なエネルギーを生み出すことを目指す「人工太陽」の研究が中国で進められており、先日も新たな成果を実現して注目を集めた。
■中国の「人工太陽」EASTが新記録を樹立
安徽省にある中国科学院合肥物質科学研究院が1月20日、中国の「人工太陽」と称される全超伝導トカマク核融合実験装置(EAST)を用いて1億度を超える温度での1066秒にわたる定常長パルス高閉じ込めモード(Hモード)のプラズマ運転に成功したことを発表した。トカマク装置におけるHモード運転の新たな世界記録が樹立されるとともに、核融合炉におけるHモードの定常運転の可能性を十分に証明するもので、核融合研究が基礎科学から工学的応用へと進む大きなターニングポイントに差し掛かったことを意味する。この成果は、将来の核融合炉の建設や運用という点でも極めて重要な意義を持つという。
■世界をリードするEASTの技術
世界初の全超伝導トカマク装置であるEASTは、2006年の稼働開始以来、15万回以上のプラズマ運転を行い、ほぼ100万個という膨大な数の部品が寸分の狂いも生じることなく動作してきた。その性能は定常プラズマ運転の工学および物理分野において、国際的な最先端の地位を維持しており、長パルスHモード運転において、これまでに60秒、100秒、400秒といった重要なマイルストーンを次々とクリアし、今回ついに1000秒の大台突破という偉業を成し遂げた。
■可能性を秘めた「Hモード」の課題を克服
研究チームによると、Hモードでの運転は効率が高く、経済性にも優れるため、将来の核融合実験炉および商用核融合炉の定常運転における基本的な運転モードとして期待される一方で、高閉じ込め状態においてプラズマの周辺領域で温度・密度の急激な崩壊が発生するという大きな課題があるという。この崩壊過程で発生する強い熱流がダイバータ(プラズマの不要な粒子や熱を排出する装置)の熱負荷を著しく増大させ、プラズマの周辺部から放出された高エネルギー粒子がターゲットプレートに衝突してプレートの材料損傷やスパッタ(飛散)を引き起こし、多量の不純物がプラズマの中心部に侵入することで、大規模な崩壊現象を誘発する可能性があるとのことだ。
核融合反応を制御するため、研究チームはプラズマの中心部と境界領域の統合制御、プラズマと壁の相互作用、精密制御、リアルタイム診断、能動冷却など、最先端の物理・工学技術に関する一連の課題を克服し、1億度超という極度の高温下において、従来よりはるかに長い1066秒というのHモードプラズマ運転を実現した。実際に人工太陽をエネルギー源として日常的に利用するにはまだまだ遠い道のりが必要とのことだが、今回の新たな成果によって少なくとも太陽に「一歩近づいた」ことは間違いないようだ。
(出典:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1821769493170601872)