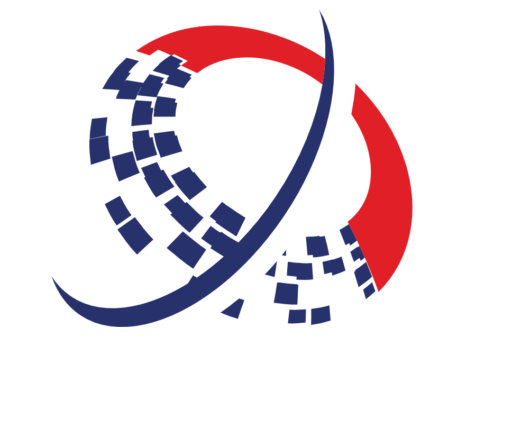中国で、春になると市場に出回る「香椿(シャンチュン)」。日本ではあまり見かけない食材だが、中国ではこの「香椿」の新芽が春野菜の定番だ。

POPにおすすめの調理方法が紹介されている

上海の市場では1束で約204円
「香椿」は、日本で「チャンチン」と呼ばれるセンダン科の落葉高木で、庭木や材木などに利用されている。食用としてはあまり知られていなく、世界でも唯一食用としているのが中国だと紹介されるくらい、日本人にはなじみの薄い食材だ。ちなみに中国の北方では春を告げる野菜とも呼ばれ、この「香椿」を食べないと「春」は来ないとまで言われる。

香椿と卵の炒め物(出典:百度百科)
さて、「香椿」という漢字から、かなり香りが良いのではないかと思うかもしれないが、実際はそのイメージを簡単にくつがえす「臭気」が強い食材だ。独特の香りと言うと聞こえはよいが、一言で表現することが難しいほどの「におい」で、強いて言うならばドクダミのにおいが混じったような、草の青みも感じる何とも言えないにおいなのだ。パクチー同様に好みがはっきり分かれる食材だとも言える。ただ、一度その「におい」にはまったら、もう毎年、春が来るのが待ち遠しくなるほどやみつきになる食材であるところもパクチーに似ている。
「香椿」の食べ方だが、豆腐とあえたり、卵といっしょに炒めたりして食べるのが中国では一般的。シンプルなだけに「香椿」そのものの味がいかされて、香りはとても濃い。後味に残る苦みも特徴で、卵と炒めたときにその苦みがアクセントになり、くせになる味でもある。
「香椿」は栄養もあり、ビタミンを含んだ健康食品としても研究され、評価が高い。味が苦手な人は身体に良い「薬」だと思って食べれば、そのにおいも気にならないかもしれない。

取れ立て新鮮野菜が並ぶ市場
この「香椿」が出回る時期に食べると、季節の変わり目におこる体調不良などの改善にも効果があるとも言われ、こうした習慣から見ると、自然と「旬のもの」「時期のもの」を取り入れる中国人の食生活には、まさに「薬食同源(薬を飲むことと食べものを食べることは同じくらい大事である)」という中医学の思想が流れていることを感じる。
日頃から家庭料理にも自然と取り入れている、中国ならではの食事健康法はまだまだ沢山あると思うが、この時期にしか味わえない春野菜の「珍味」、日本でのブームも近い?!
※株式会社フライメディアは、中華圏と日本をつなぐ会社です。
本日御紹介した「旬の中国野菜」関連の取材したい、もっと詳しくリサーチしてほしい、写真や映像を使用したいなどご要望がございましたら、是非弊社にお問い合わせください!