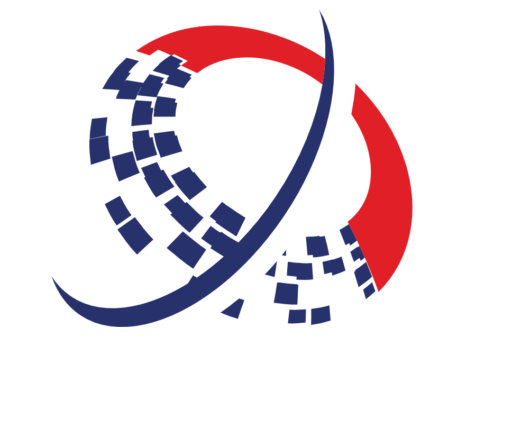■シューマイ、日本でも中国でも愛される点心
日本で「中華料理と言えば」と聞けばきっと5本の指に入るであろう、焼売(シューマイ)。人気度から言うと餃子(ギョウザ)にはかなわないかもしれないが、スーパーに行けば必ずと言っていいほどチルドシューマイや冷凍シューマイが売られているし、横浜生まれの崎陽軒の「シウマイ」は全国にその名が知れ渡っている。本場中国でもシューマイは北西部や東北部のほか、香港でも特に親しまれている。今回は、香港のシューマイにまつわる話だ。
■肉まんから派生? シューマイの起源を探る
まずは、シューマイの起源について紹介しよう。諸説あるようだが、一説には肉まんの「包子」(パオズ)を起源として、今から約700年前に誕生したといわれている。一般的には「焼売」と書くが、中国では「焼麦」との表記が多く、どうやらこちらのほうが歴史が古いようである。このほか、「稍麦」「焼梅」「鬼蓬頭」なんて呼ばれることもあるという。

ではなぜ「焼売」という字が当てられるようになったのか。その昔、あるホテルで客足が減り、肉とご飯が大量に余ってしまったという。そこで料理長が肉とご飯の肉を細かく刻み、残りのご飯と混ぜ合わせて水餃子の皮で包んだが、餡が多すぎて皮を閉じきれず、上部が開いた形になった。これを蒸してみたところ非常においしく、店で売り出したら大人気に。「これは上が開いていて、餃子でも包子でもない。何と呼べば良いか?」と尋ねる従業員に対し、経営者は「焼いて売るから『焼売』だ!」と答えたという話があるようだ。
なお、モンゴルから南下し進化したという説もあり、もともとは羊肉が具として使われていたという。それが南下するに従って豚肉やエビといった具材を用いるようになったとか。そう言えば、中国東北部で食べられる「焼麦」の具はもち米と豚肉を混ぜたものだった。ということは、ホテル発祥説もあながち間違いではないのかもしれない。
■香港人の暮らしに根づいたシューマイ文化
ここからはいよいよ、香港のシューマイ文化について触れていこう。焼売は、朝食、アフタヌーンティー、夜食を問わず、香港人の生活に欠かせない存在となっており、特に肉体労働者は忙しい仕事の合間に串刺しにした魚肉シューマイを食べて空腹を満たしてきたようで、それが彼らなりの「アフタヌーンティー」になっているという。
この魚肉シューマイこそ香港を代表するシューマイと言える。戦後、香港の飲茶文化が急速に発展する中で、豚肉や海老のシューマイが人気を博していたが、やがて街頭の屋台がコストを抑えるために小麦粉と魚肉を使った魚肉シューマイを作り出し、それが現在まで広く知られるストリートフードへと発展したそうだ。

■ジャンキーで愛されるストリートフード
魚肉シューマイに使われる魚は安価なもので、しかも小麦粉とタピオカ粉を増やすことでさらなるコストダウンが図られているのだが、粉が増えることによって独特のプリプリモチモチ感が増大するという。そして胡椒、醤油、うま味調味料をドバっと注ぎ込んで味を整える。チープであればあるほど、ジャンキーであればあるほど市民から愛されるのが魚肉シューマイなのだという。贅沢に高級魚をふんだんに使い、小麦粉やタピオカ粉を減らしたものは「お上品すぎてジャンキーさが足りない」と不評を買うというからおもしろい。
この魚肉シューマイと魚蛋(フィッシュボール)が香港のストリートフードのツートップだという。港町ゆえの根強い魚食文化が垣間見える。
■黄色い皮に込められた「幸福」と「繁栄」
なお、香港のシューマイは「皮が黄色い」という特徴も持っている。卵黄やカニの卵で着色するそうだが、より魅力的で美味しそうに見せ、視覚的な食欲を刺激するという理由のほかに、黄色が中国で「富貴、繁栄、好運」を象徴する色として特に好まれてきたという要因もあるようだ。幸福と幸運を呼ぶ食べ物、ということで皮の黄色いシューマイが好んで作られ、食べられるようになったのだろう。

香港ではシューマイやフィッシュボールを食べることを、串に刺す動作に由来する「篤」という言葉でしばしば表現される。香港のストリートグルメを堪能したければ、ぜひとも黄色い魚肉シューマイを「篤」してみよう。